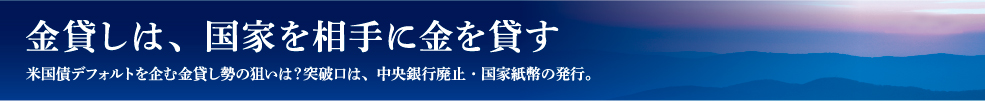2014-01-29
金貸しによる洗脳教育史②〜皇帝と教皇の詭弁合戦から大学が生み出された

教育機関の頂点に位置し、学問の権威的存在となっている大学機関。今回はその大学の起源に迫ります。
一般的には大学の起源は12世紀のボローニャ大学、パリ大学とされ、それらは自然発生的に成立したと説明されていますが、よくよく事実を見てみると権力争いに端を発していたという新たな側面が見えてきます。
まずはその当時の時代背景から。
【特集:デフォルト研究】(6)バランスシートって何?
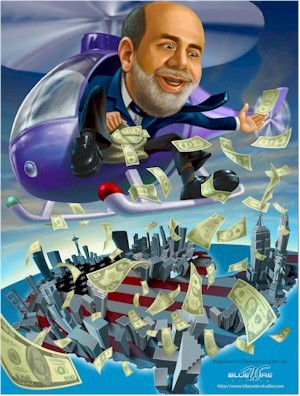
前回は、これまでの中間整理を兼ねて、「’13年総括、デフォルトスキムの整理」としてまとめました。
その中でも、「帳簿操作による借金帳消し」。これが新しいスキムとして注目です。
では、帳簿操作で借金帳消しとは?どのようの行われるのでしょうか?
そのもととなる「バランスシート」について、今回は調べてみました。
いつものブログ応援もよろしくお願いします。
金貸しによる洗脳教育史①〜プロローグ
新年明けましておめでとうございます 
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます 
新年に入って早速ですが、新シリーズを始めます 
年次改革要望書、郵政民営化、直近ではTPPなど、日本ではこれまで官僚主導でアメリカに有利な政策が進められてきた。その中でも中心になって動いてきたのは、フルブライト留学制度やローズ奨学金制度などでアメリカの教育を受けてきた官僚たちである。
また、日本の庶民がこうしたアメリカに都合の良い政策を受容れてしまう背景に、戦後教育により植え付けられた個人主義、民主主義、市場主義等の思想があるが、これも又、欧米から持ち込まれた教育制度の賜物である。
教育機関は、近代以降、金貸しが国家や民衆を支配していくための洗脳の道具になっている。

金貸したちにとって教育とは、どんな意味を持つのだろうか?
「感謝の心を育むには」ブログより引用します。
(家庭ブログより)
彼らの、「教育」に対する価値感は家畜同様の「調教」にあるのではないかと思います。
そう考えると、キリスト教(プロテスタント)では、教職者を「牧師」と呼んでいます。そして、「迷える子羊」を導いているのです。
或いは、羊の群れを思いのままに操るには、群れのボス的存在を抑えておけば、その他はボスに追従するという発想から、ローズ奨学金やフルブライト留学制度などが行われ、或いは、幕末〜明治初期の薩長や政府要人の留学や使節団の受け入れなども、その後の倒幕や明治新政府の「支配」を容易にするためのものであったと思われます。
公教育は、そういう意味では、指導者に従わせるための「調教」そのもので、キリスト教から派生した近代思想によって、「羊は羊として生きること」と「支配」を変ることのない現実として、頭の中に「実現されることのない理想(夢)」を想い描かせるためのものだったのです。
そして、群れの中では、まとまって歯向かってこないように、或いは、社会全体のことに目が向かわないように、「個人主義」を教え、「自由」や「人権」など「微妙な対立構造」を仕組み、仲間や集団ではなく「群集」として育て挙げてきたのです。
金貸したちは、中央銀行制度による資力による支配、軍やCIAを使った武力と脅しによる支配、宗教やマスコミ、教育を使った思想・価値観の支配の三軸の支配構造によって、世界を思うままに動かしてきた。
しかし、共認原理に移行しつつある現代、武力支配は行き詰まり、中央銀行制度による資力支配も国の借金が限界を超え、制度自体がガタガタになってきた。しかし、思想や観念の支配は、いまだ大きな力を残している。従って、金貸し支配からの完全脱却には、この洗脳支配から脱する事が必要不可欠となる。
そこで、歴史をさかのぼって、教育に着目し、金貸しの支配の方法論を明らかにしていく新シリーズをスタートさせます。
 目次・流れ
目次・流れ 
1.大学の起源/大学って誰が何のために作ったの?
2.金貸したちが作った米国の大学
3.明治維新〜日本に持ち込まれた西洋思想
4.義務教育はなぜ始まったのか?
5.戦後民主教育
まずは、大学の起源から追求していきます。
【幕末維新の代理人】代理人認定#12 岩崎弥太郎 第6回〜明治維新の激動に紛れた俄分限 三菱・弥太郎の軌跡〜
新年あけましておめでとうございます 
昨年は、特定秘密保護法の公布(12月13日)や日銀の異次元緩和を始めとし、国民の十分な合意や理解を得ないまま、国家権力を増長させる方向に日本社会が動きました。2014年以降もこの傾向は変わらず、残念ながらあまり明るい未来にはならないと当ブログは見ています。
これら政府や日銀の動きは、とても国民や国家を守る行動とは思えません。なぜこうなってしまうのでしょうか?
それは、政治家や官僚は金貸しによって支配、操作されているためです。己の利権を守るためには、(国民よりも)まず金貸しの支持を得なければならない。この構造から脱却しない限り、金貸しによる国家支配は続きます。
昨年からお送りしている【幕末維新の代理人】シリーズでは、この金貸しの支配構造が生まれた、幕末〜明治に焦点を当てています。欧米列強の武力によって、幕末の開国=市場開放がなされ、明治政府の樹立=近代国家の成立も背後にいた金貸しの思惑によるものでした。
この激動の時代に名を馳せた著名な人物のうち、欧米列強の金貸しの力を利用、あるいは彼らと結託して、日本の内側から開国の鍵を開けた人物たちがいます。それらの人物にスポットを当て、現在も連綿と続く金貸しの支配構造を明らかにし、それを広く知らしめ、来る日本社会を明るいものにしたいと考えます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回は、昨年4回に渡ってお送りした三菱・岩崎弥太郎シリーズの総集編をお送りします。
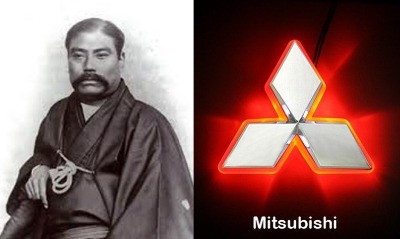
◆弥太郎と三菱の歩み
下の画像は、東京駅周辺で三菱グループが所有するビルを示したものです。

(写真は こちら よりお借りしました)
資力が武力を上回ったのはなんで?(3)〜武力が制覇力になりえなくなった時〜
☆☆☆☆☆ 新年 明けまして おめでとうございます 

☆☆☆☆☆ 今年が皆さまにとって良い年になりますように 

☆☆☆☆☆ そして当ブログを今年も可愛がってくださいませ 

さて、このシリーズでは、「資力が武力を上回ったのはなんで?」を扱っています。これまでの記事はこちらです。
(0)プロローグ
(1)“公共事業”としての十字軍と周辺ビジネスで肥大化した「騎士団」
是非、どうぞ 
 今回はスイスが世界に与えた影響について扱っていきます。
今回はスイスが世界に与えた影響について扱っていきます。

1291年にスイスは独立国家として誕生しましたが、険しい土地ゆえに耕作面積も少なく、国家を維持するには出稼ぎに出て外貨を稼ぐしか手がありませんでした。
そこでスイスは、1314年モルガルデンの戦いで広まった“強いスイス軍”の評判を追い風に、傭兵産業を確立させます。これは前回記事でも取り上げましたが、周辺国と武力協力することで、負け組でありながら、生きながらえる戦略でもありました。それでいて外貨を稼ぐ立派な産業だったのです。
もちろんそれまでに“傭兵”は存在していましたが、おそらく“あぶれもの”が中心だったでしょう。したがって、“腕っぷし”と国家産業としての“信用力”を兼ね備えた兵ですから、他国にとっては有難い供給源だったと思われます。
日本で“傭兵”というと雇われ兵士で、小規模なイメージですが、さすがヨーロッパはスケールが違います。スイスのお膝元であるイタリアが傭兵の活躍の場でしたが、軍隊のほとんどが傭兵という例もあるそうです。そしてその暴れっぷりの様子が、ブログ「傭兵たちの略奪」の記事に記載されていましたので、紹介します。
とその前に、応援のポチをお願いします。
アメリカ・デフォルトは起きるのか!?-5 〜金貸しは国家を見限り、直接支配に乗り出した!?〜

こちらより拝借しました
お正月ということで、今年含め、これからの未来がどのようになっていくのか?を考察したいと思います。
新年早々故、明るい未来を描ければと思っていたのですが、米国債デフォルトを巡る状況をつぶさに見ていくと、どうもそうも言ってはいられません。
逆に、とっても恐ろしい未来が待ち受けているのではないか?という結論に達してしまいます。
前回の記事『アメリカは世界支配に向けた壮大な実験場!?』では、ロスチャイルドが画策する米国債デフォルトとは、実は世界支配に向けた布石で、アメリカはそのための実験場にされているのでは!?という大胆な仮説を立てました。
その背景には、国家に巣食った中央銀行制度は、国家の借金を増大させ返済不能に陥り、さらには、国家の存続さえ危うくさせる。つまり、共倒れにならざるを得ないという構造があるからです。
さらに、その根底には、人間の欲望は際限がない=物的需要は永続的につくり出されるという経済理論が、消費欠乏の衰弱という人々の意識という現実により崩れ去ったことにあります。
そして、それに気付いた金貸し、現在の主力はロスチャイルドですが、それまでのシステムを考え直さなければならない事態に陥っています。
また、リーマンショック前夜から始まった、(戦争への道を半ば閉ざされ)金融世界に食指を伸ばしてきたロックフェラーに対し、それを迎え撃ったロスチャイルドとの戦いにより、それまで門外不出であった双方の国家支配の手口が、敵対し合う双方からのリーク:暴露という形で、主にインターネットを通じて広がり、彼らの存在と支配の仕組みが、一般庶民に明らかにされつつある状況は、彼らの危機意識を相当高めていることは容易に推測できることです。
彼らが最も恐れることは、集団としてまとまり対抗してくることです。
2014年迎春
明けましておめでとうございます。
本年も、『金貸しは、国家を相手に金を貸す』をどうぞよろしくお願い致します。