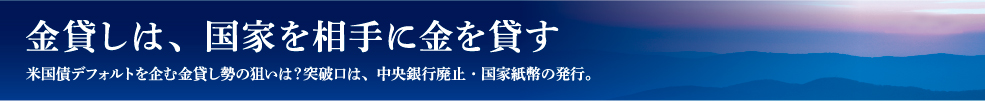2009-12-31
新政権の22年度予算編成、特別会計への切り込み不十分
今日は大晦日、2009年の最大ニュースは政権交代ですね。
前回の新政権予算、亀井語録の意図を読む。特別会計の埋蔵金に切り込め!に続け、今回は22年度予算を扱います。
1.新政権の力量が問われた予算編成
新政権は、対米自立路線、官僚依存からの脱却を目指しています。
官僚依存からの脱却、その最初のハードルが、22年度当初予算の編成でした。官僚の力を借りずに、民主党が自前で予算編成できるのか、官僚達の有形無形のサボタージュを乗り越えて、国の歳入と歳出を組みかえれるのか?
野党時代に、国政・予算に対する原則をどのように考えてきたか、どこまで官僚達の誤魔化しを見抜いていたのか、苦境の中にある国民の活力をどう引き出そうとしているのか、新政権の力量と能力が試される局面です。
果たして、どうであったか。亀井大臣の「主計局長の首を切っても、積極財政を組め!」は実行されたのでしょうか?
12月25日に決定した「22年度一般会計予算案」を切開してみよう。
原口大臣の頑張りもあって、地方活力再生のために、地方交付税等を1兆円上乗せさせた。
しかし、官僚中の官僚である財務省の枠組みに終始した感があります。
①大不況による大幅な税収減を、財務省主税局から突きつけられた。
「積極予算を組んで、50兆円以上の国債を実行すれば、国家は破綻するがそれでよいか!」と。
旧来は、甘めの税収見通しで組み、見かけ上の国債発行額を低くく押さえていたのですが、今回は大幅税収減を最初から出してきて、ハードルを高くしました。
財務省の脅しと懐柔策です。
②特別会計の埋蔵金は特殊一時財源だと洗脳された。
「国民新党のいう、10兆円、20兆円の積立金(埋蔵金)は、恒常的財源ではない。22年度に使い切ってしまうのか?」と。
③特別会計の積立金(埋蔵金)は、将来リスクの対応だとごまかされた。
「外為会計積立金は、円高差損の積立だ。労働保険の積立は、将来負担のためである。」
本文を読む前に、クリックを!
【需要発から供給発へ】5.新概念を使いこなせて、はじめて供給者になれる
【需要発から供給発へ】シリーズバックナンバー
1.働かない人に支援金を払って、活力が上がるわけがない
2.「役に立つ答えを探す事」が、社会活力の基礎構造
3.活力再生需要に対しては、『供給者不足』
4.「需要発から供給発へ」
前回のエントリー「需要発から供給発へ」では、
「これまでの市場経済の需要発の発想」を超えて「類的供給体制の整備=供給者の育成」という視点で、補助金(否、手垢についた補助金という言葉は止めて活力再生事業者支援金と呼ぼう)を「子育て支援」活動や「老人のやりがいづくり」活動や勿論「共認形成」活動に払っていけば、供給者はどんどん誕生していき、日本は世界経済のまさに最先端を切って、新たな類的生産の時代を開いていける。
という「需要発から供給発」の認識転換が、今の市場を突破する切り札になる!という提起であった。
しかし、「活力再生需要に対しては、『供給者不足』」でも提起されているように、現状は活力再生需要に応える「答え」の供給者が圧倒的に不足している。
ではどうやったら、答えの供給者になれるのだろうか?
今回は「答えの供給者になるには?」の“答え(=可能性)”の根幹を示した記事を紹介したい。
いつもありがとうございます!続きを読む前にポチッとお願いします!
ドルに代わる通貨システムは?〜11.新しい通貨システムの必要条件は?
 本シリーズでは、ドルに代わる国際通貨システムがどのように変わっていくのか、最近の動きを追いかけながら記事を書いてきた。その間にも、ドバイ・ショック、民主党の中国への接近、ウォール街の金融機関たちの収益回復(ただし見かけ上)などの動きが起こった。しかし、中期的に見て米国=ドルの衰退は不可避である。
本シリーズでは、ドルに代わる国際通貨システムがどのように変わっていくのか、最近の動きを追いかけながら記事を書いてきた。その間にも、ドバイ・ショック、民主党の中国への接近、ウォール街の金融機関たちの収益回復(ただし見かけ上)などの動きが起こった。しかし、中期的に見て米国=ドルの衰退は不可避である。
今後、世界がどのように動いていくのか?これは、金貸しや欧州奥の院の動き、米国の崩壊状況、中国バブルの動向、そして日本の出方次第で大きく変わる。しかし、より巨視的に見れば、現在進行中の経済危機は、300年間続いた金貸し支配の終焉、そして資本主義・市場社会が大きく変質していく始まりである。では、もう少し先の未来、通貨(お金)はどうなっていくのか?より根本的な部分からイメージを試みて、本シリーズの一旦の区切りとしたい。
いつも応援ありがとうございます。
宇宙船地球号パイロットのマニフェスト(5) トリウム・エネルギーが生むポスト・ドルの準備通貨「UNI」
冒頭筆者は、一事業家であると自己紹介しました。いやむしろ、今ここに新しいビジネスモデルを提起していることからすれば、一起業家(アントレプレナー)であるという方が当っているでしょう。そこには、ソシアル・アントレプレナーとして、ビジネスモデルをもって人類の全面的崩壊に立ち向かうことができるという自負があるからです。
何せ68歳で新規に起業しようとするわけですから、今さら目先収束をするわけにはいきません。国連という舞台におけるスティグリッツ博士や、デスコト前総会議長の国際通貨金融システム改革の闘いに、声援を贈っていればそれでいいというわけにはいきません。単一の超国家的準備通貨実現のためには、ビジネスの力をもってペアとなる車輪をつくり、合わせて両輪となす闘いを欠かすことはできないと考えています。
ということで、5回目をお届けしますが、例によって今後の進捗を一覧にしておきます。バックナンバーについては、リンクになっています。
1.「石油・ドル本位制」に代わる世界システムをつくる
2.石油に代わる代替エネルギー資源としてのトリウム
3.人類が必要とする8万kWe、84万基のトリウム原子炉
4.トリウム原発によるBOP優先の安価な電力供給計画
5.トリウム・エネルギーが生むポスト・ドルの準備通貨「UNI」(本稿)
6.地域通貨「アトム」から国際準備通貨「UNI」への出世街道
7.「見えざるカミの手」による布石か? シーランド要塞跡
8.金融崩壊の今こそ、金融再生を担う新しい人材が必要
9.工程表に従い、エンジニアリング企業とシーランドを確保
10.2050年の人口を基に策定したマーケティング・エリア
11.総額1680兆円の建設費を要するトリウム・エネルギー
12.トリフィン・ジレンマのない「アトム」だから「UNI」に出世できる
13.ケース・スタディとしての「朝鮮半島エリア」(上)
14.ケース・スタディとしての「朝鮮半島エリア」(下)
では始めましょう。その前に、クリックをお願いします。
GDP信仰からの脱却3〜GDPとは“市場化”された活動の総量
前回記事で、GDPとは「国内を流れたお金の流量」である、と書いた。では、それと、GDPの定義「国内で産み出された付加価値の総額」との関係はどうなっているのか。これを見るため、今回はGDPの「三面等価の原則」について考えてみる。
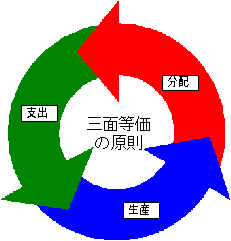
いつも応援ありがとうございます。
経済学って正しいの?13 『 政府紙幣を発行してもハイパーインフレは起こらない 』
『 経済学って正しいの?』と謳ったシリーズ 第13弾です。
前回は政府紙幣の仕組みについて触れました。政府紙幣の発行というと、すぐに「ハイパーインフレ」を懸念する声が聞かれますが、前回検証した通り「デフレギャップ」が生じているうちはインフレが生じることは無いことが分かります。
今回は、過去の政府紙幣の事例を検証しつつ、引き続き政府紙幣の可能性を探っていきたいと思います。

50銭政府紙幣(昭和23年3月10日〜昭和28年12月31日)
『商品市場の背後に性市場あり』 その4 ・・・ 性権力を正当化する欺瞞思想=近代思想の正体

前回は、市場拡大の原動力となった『近代思想のペテン』がなぜまかり通ったのか?近代思想がどの様にして実を結んだのか?について扱いました。
今日はその続きです。
まずは応援よろしくお願いします。
↓
剥き出しの自我を覆い隠す『権利』という正体、そして近代思想の背後にある『権利』が要求・権利主義を加速させ、本源価値を破壊してゆく極めて悪質な欺瞞観念である。
今回は、これらについて見ていきましょう。
引き続き『実現論 第二部私権時代 チ.性権力を正当化する欺瞞思想』より引用してゆきます。
新政権予算、亀井語録の意図を読む。特別会計の埋蔵金に切り込め!
新政権発足以降3ヶ月、亀井金融担当大臣による予算関連の言動が世間を騒がせ注目を集めている。特に気になるのが裏付けとなる財源問題である。亀井大臣の発言に焦点をあてて、その意図を探ってみたい。
亀井静香公式サイトより引用
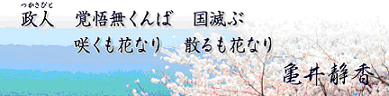
アメリカ型グローバリズム・・弱肉強食の市場原理至上主義が横行・・・弱者が切り捨て・・深刻な格差社会・・・
辛いときこそ支えとなり万人に生きる喜びと希望を与えるのが国家の役割であり、政治家の務めです。
アメリカに追従するだけでなく、同盟国として対等な立場に立ち自らの方法で世界の平和と安定のために貢献。
上記のサイト、特にその和歌に亀井大臣の政治理念や心情がよく表われているように思う。
財源問題解決の秘策が何処にあるのか国士亀井大臣の言動から追求してみます。
本文を読む前に、クリックををお願いします!
【需要発から供給発へ】4.「需要発から供給発へ」

(エコカー減税をアピールする「こども店長」の加藤清史郎クン。)
【需要発から供給発へ】シリーズでは、経済破局を突破するための答えを探るべく、るいネットより
1.働かない人に支援金を払って、活力が上がるわけがない
2.「役に立つ答えを探す事」が、社会活力の基礎構造。
3.活力再生需要に対しては、『供給者不足』
の投稿を紹介してきました。
前回のエントリー「活力再生需要に対しては、『供給者不足』」では、物的需要は供給過剰だが、活力再生需要に対しては供給者が不足しており、供給者を支援していく仕組み作りが必要であることを述べました。
しかし一般の企業は「活力再生需要」の存在に気付いていません。なぜでしょうか?
それは、社会は既に物的に飽和しているにも関わらず、これまでの物的需要を前提とした「需要発」の思考(需要はどこにあるのか?)に囚われているからです。
では「需要発」ではなく、どのように考えたらよいのでしょうか?
そこで今回は、「需要発から供給発へ」を紹介しながら、需要発の発想の限界と、供給発の発想へ転換することでの可能性を見ていきます。
応援よろしくお願いします☆
宇宙船地球号パイロットのマニフェスト(4) トリウム原発によるBOP優先の安価な電力供給計画
前回も冒頭に述べましたが、非電化地域の住民であるBOP(ボトム・オブ・ザ・ピラミッド)にこそ、優先的に電力を届けることが筆者の悲願です。BOP優先は、否応なしに低コストを迫ります。既存のウラン−プルトニウム・サイクルの原発による発電コストには、公表されない隠れコストも云々されていますが、発電所建設のコストの8割は、苛酷事故に対するセキュリティにかかるコストであると言われており、苛酷事故のないトリウム原発では不要なコストです。もちろんトリウムとウランの原料価格にも大差があります。
したがってBOPへの電力供給に適うエネルギー源は、今のところトリウムをおいては考えられません。この事実を共認することによってこそ、生産的な次世代エネルギー論を展開できるのではないでしょうか。それでは議論を先に進めることにしましょう。
ということで、4回目をお届けしますが、例によって今後の進捗を一覧にしておきます。バックナンバーについては、リンクになっています。
1.「石油・ドル本位制」に代わる世界システムをつくる
2.石油に代わる代替エネルギー資源としてのトリウム
3.人類が必要とする8万kWe、84万基のトリウム原子炉
4.トリウム原発によるBOP優先の安価な電力供給計画(本稿)
5.トリウム・エネルギーが生むポスト・ドルの準備通貨「UNI」
6.地域通貨「アトム」から国際準備通貨「UNI」への出世街道
7.「見えざるカミの手」による布石か? シーランド要塞跡
8.金融崩壊の今こそ、金融再生を担う新しい人材が必要
9.工程表に従い、エンジニアリング企業とシーランドを確保
10.2050年の人口を基に策定したマーケティング・エリア
11.総額1680兆円の建設費を要するトリウム・エネルギー
12.トリフィン・ジレンマのない「アトム」だから「UNI」に出世できる
13.ケース・スタディとしての「朝鮮半島エリア」(上)
14.ケース・スタディとしての「朝鮮半島エリア」(下)
では始めましょう。その前に、クリックをお願いします。