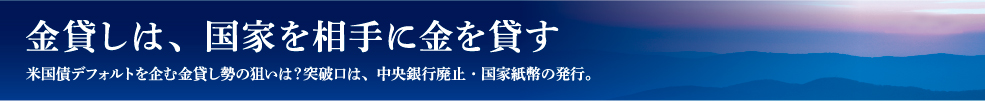2013-03-28
お金はどこから生まれてきたのか?〜中国における貨幣制度の成立
このシリーズでは、私たちの暮らしになくてはならない「お金」というものが、どこから生まれてきたのか?を追求しています。
人類の歴史は、かつて共認によって集団及び社会統合していた時代から、武力による統合へ、そして現代につながる貨幣による統合へと移行してきました。このうち武力から貨幣へと移行する結節点を探ろうというのが、そもそもの問題意識です。そこに貨幣制度の持つ強さや恐ろしさ、欠陥が見えてくるのではないかと期待しています。
今回は、そのうちの貨幣成立の歴史:中国編の最後になります。
さて前回までの記事はこちらです。
第1回 プロローグ
第2回 パプアニューギニアでの貝貨の使われ方
第3回 中国、殷の時代に宝貝はどのように用いられたか?
第4回 中国での貨幣登場

前回の記事では、幻想価値であった宝貝の代わりに、贈与品として実用価値を持った青銅器が登場したことを扱いました。
殷の生き残りである「専門技術集団」が青銅器精錬技術を発達させたことによって、青銅器の刀や農機具が発達し、それぞれ兵士や農民にとって貴重なもの、必要なものとして広まっていったのです。これにより交換市場が形成されました。ただ初期段階では実質的には物々交換のようなもので、それが市場の交換ツールに特化することで刀銭、布銭が登場したのです。*写真は周朝時代の青銅刀
実は、周が殷を滅ぼした殷周革命での重要ポイントとして、「殷の生き残り集団」がもたらした歴史的意味が、「青銅器技術を向上させたこと」以外にもう一つあります。今回はそこから改めて刀銭・布銭が広まり「貨幣」成立へつながる経緯に、アプローチしていきます。
【幕末維新の代理人】代理人認定#2 井上馨 〜攘夷→開国→倒幕→欧化政策 結局守ったのは己の利権?〜
「日本において、体制の変化が起きているとすれば、それは日本人だけから端を発しているように見えなければならない」
「事実、その変化はわれわれの考え方と異なる仕方でおきるかもしれないがそれが真に恒久的なものであり、且つ有益なものであるためには、徹頭徹尾、日本的性格という特徴を帯びていなければならない。」
(1866年4月26日、ハモンド外務次官からパークス在日公使館宛文書・・・遠い崖−アーネスト・サトウ日記抄3『英国策論』 より転記)
このシリーズは「幕末維新の代理人」をテーマに、近代以降における金貸しの日本支配の構築過程に着目、実際に金貸しの代理人=エージェントとして動いていたであろう人物達に焦点を当て、これまで語られなかった幕末維新の背景を明らかにしていくものです。
これまでのシリーズは、
【第1回】プロローグ
【第2回】黒船前夜〜アヘン戦争と英国による間接統治〜
【第3回】黒船来航〜ロスチャイルドのエージェントだったペリー〜
【第4回】幕末の下級武士たちを突き動かした役割不全と私権不全
【第5回】「攘夷を旗印に暴れた下級武士」と「倒幕に突き進んだ西国雄藩の本音」
【第6回】【幕末維新の代理人】代理人認定#1 伊藤博文〜日本最初の総理大臣は、金貸しによって作られた
をお送りしてきました。
前回記事でお伝えしたように、
この金貸し支援政府の伊藤第一次内閣において、初代外務大臣(外務卿)となったのが井上馨です。今回はこの伊藤博文と同じく長州の雄であり、また英国に密航留学した長州ファイブの1人でもあった井上馨に迫ってみます。
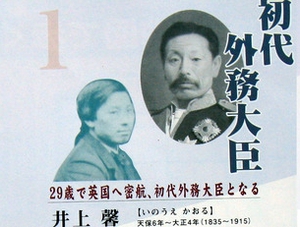
【井上 馨(いのうえ かおる)】
大恐慌の足音・企業は生き残れるか?第10回 〜日本マクドナルド・ホールディングス株式会社〜
前回までは、電機・工業品メーカー、流通業界における企業の経営状況分析をしてきました。
どの分野でも、少なからずリーマンショックの影響を受けており、経営状況が悪化した企業や逆境を乗り越え挽回をみせる企業など、生々しい企業の実態を垣間みることが出来ました。
今回からは路線を替え、食品産業界に視点を向けてみたいと思います。
近年急速に高まってきている人々の食への関心は食品業界にどのような影響を与えているのでしょうか。
今回扱う企業は、あの馴染みの深い『日本マクドナルド・ホールディングス株式会社』です。

いつも応援ありがとうございます。
日本史から探る脱市場の経済原理(12)〜日本人の中に息づく鎌倉武士の精神性〜
前回記事では、鎌倉武士の成り立ちと生活を取り上げました。
鎌倉武士は武士の理想像とされます。鎌倉時代が終わって南北朝の動乱、室町期、戦国期、江戸期を通じて「古の鎌倉武士を見るような」との賛辞は武士を褒めるのに最大級のものであったことは確かです。武士の精神は鎌倉期に極限まで高揚し、南北朝、室町期に低迷し、もう一度戦国期に高揚しますが、戦国武者をもってしても鎌倉武士の下位におく人が多いです。
こちらより

今回は、彼らの精神性の中味をより具体的に見ていきたいと思います。
【15】『世界経済の現状分析』コラム:新たな天然ガス資源「シェールガス」

<画像リンク>
前回は「ロシア経済の現状分析」として、プーチン政権が米国のシェールガス革命に焦り、資源を主軸とした国家運営は輸出先の経済状況や各国のエネルギー事情に大きく左右されている背景があり、その「焦り」の中身について見てきました。
今回は近年、話題となっている新たなエネルギー開発の中でも注目高い、シェールガスについて調べてみたいと思います。
『世界経済の現状分析』シリーズ過去記事は以下をご覧ください。
『世界経済の現状分析』【1】プロローグ
『世界経済の現状分析』【2】米国経済の現状(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【3】米大統領選の分析その1(両候補の政策の違い)
『世界経済の現状分析』【4】米大統領選の分析その2(両候補の支持層の違い)
『世界経済の現状分析』【5】米大統領選の分析その3(米大統領選の行方?)
『世界経済の現状分析』【6】中国経済の基礎知識
『世界経済の現状分析』【7】中国経済の現状(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【8】中国、新体制・習近平でどうなる?
『世界経済の現状分析』【9】中国経済のまとめ
『世界経済の現状分析』【10】欧州経済の現状①(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【11】欧州経済の現状②(独・仏 VS PIIGS 格差問題の分析)
『世界経済の現状分析』【12】EU経済の現状③(EUの政治状況、右翼化?)
『世界経済の現状分析』【13】ロシア経済の現状(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【14】ロシア経済の現状〜プーチンの焦り
お金はどこから生まれてきたのか?〜第4回 中国での“貨幣”の登場♪〜

皆さん、こんにちは♪
【お金はどこから生まれてきたのか?】シリーズも今回で4回目になりました

 今までアップしてきた記事はこちらからどうぞ^^
今までアップしてきた記事はこちらからどうぞ^^ 
第1回 プロローグ
第2回 パプアニューギニアでの貝貨の使われ方
第3回 中国、殷の時代に宝貝はどのように用いられたか?
前回は、殷では、パプアニューギニアで友好の証として贈られた宝貝が国家統合のしくみに組み込まれ、支配服属の関係を補強するために使われていたことを明らかにしました☆
今回は、部族連合の神権国家が解体された周の国家で、宝貝の使われ方がどのように変化していくのか?を追求してみたいと思います♪
『世界経済の現状分析』【14】ロシア経済の現状〜プーチンの焦り

前回は、ロシアの経済ファンダメンタルズについて見てきました。
注目点は、豊富な資源(天然ガスや石油等)をもとにしたGDPのV字回復、失業率の低下、貿易力の増等。
プーチンは、豊富な資源を国有化し、金貸し達から防衛し、自国の経済の安定化を実現してきました。
一方で資源を主軸とした国家運営は、輸出先の経済状況や各国のエネルギー事情に大きく左右されます。現在プーチン・ロシアは、焦り始めています。今回はその「焦り」の中身について調べてみました。
『世界経済の現状分析』シリーズ過去記事は以下を参照してください。
『世界経済の現状分析』【1】プロローグ
『世界経済の現状分析』【2】米国経済の現状(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【3】米大統領選の分析その1(両候補の政策の違い)
『世界経済の現状分析』【4】米大統領選の分析その2(両候補の支持層の違い)
『世界経済の現状分析』【5】米大統領選の分析その3(米大統領選の行方?)
『世界経済の現状分析』【6】中国経済の基礎知識
『世界経済の現状分析』【7】中国経済の現状(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【8】中国、新体制・習近平でどうなる?
『世界経済の現状分析』【9】中国経済のまとめ
『世界経済の現状分析』【10】欧州経済の現状①(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【11】欧州経済の現状②(独・仏 VS PIIGS 格差問題の分析)
『世界経済の現状分析』【12】EU経済の現状③(EUの政治状況、右翼化?)
『世界経済の現状分析』【13】ロシア経済の現状(ファンダメンタルズ)
いつものブログランキング応援もよろしくお願いします。
大恐慌の足音・企業は生き残れるか?第9回 〜ファーストリテイリング〜
自民党が推薦し、民主党もそれを追認する形で、日本銀行総裁が元財務省出身の黒田東彦氏でほぼ内定の見通しになっています。4日の所信聴取では「デフレ脱却に向けて、やれることは何でもやるという姿勢を明確に打ち出していきたい」と強調し、阿倍政権が掲げる「物価上昇率2%達成」の目標を、「個人的には2年ぐらいを念頭におく」と発言しています。
さて、長らく続くこのデフレ基調を追い風に、そして大衆の節約志向の意識潮流にも乗る形で急成長してきた企業があります。それが、今回取り上げるファーストリテイリング(ユニクロ)です。
商品企画・生産・物流・販売までを一貫して行うSPAモデル(製造小売業)を他社に先駆けて確立し、フリース・ヒートテック・サラファインなど、高品質な商品を低価格で提供し続けて、今も尚多くの顧客を獲得しています。

衣料品業界の勝ち組企業の代表格とも言えるファーストリテイリングですが、大恐慌前夜の急速な市場縮小の状況下においても、それは全く無縁とも言えるぐらいの経営状況なのでしょうか?或いは、少なからず影響が出始めているのでしょうか?
続きはポチっとご協力をお願いします。
【13】『世界経済の現状分析』ロシア経済の現状(ファンダメンタルズ)
前回まではEU経済全体を見てきましたが、今回からは2回に渡り、ロシアに焦点を当てていきたいと思います。そこで、まず今回は【13】ロシア経済の現状(ファンダメンタルズ)と題し、最近のロシアの経済状況やプーチン大統領の公約について調べてみたいと思います。

<画像はこちらからお借りしました>
『世界経済の現状分析』シリーズ過去記事は以下をご覧ください。
『世界経済の現状分析』【1】プロローグ
『世界経済の現状分析』【2】米国経済の現状(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【3】米大統領選の分析その1(両候補の政策の違い)
『世界経済の現状分析』【4】米大統領選の分析その2(両候補の支持層の違い)
『世界経済の現状分析』【5】米大統領選の分析その3(米大統領選の行方?)
『世界経済の現状分析』【6】中国経済の基礎知識
『世界経済の現状分析』【7】中国経済の現状(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【8】中国、新体制・習近平でどうなる?
『世界経済の現状分析』【9】中国経済のまとめ
『世界経済の現状分析』【10】欧州経済の現状①(ファンダメンタルズ)
『世界経済の現状分析』【11】欧州経済の現状②(独・仏 VS PIIGS 格差問題の分析)
『世界経済の現状分析』【12】EU経済の現状③(EUの政治状況、右翼化?)
応援よろしくお願いします!