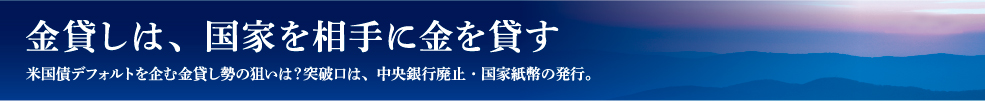2010-06-30
BRICs徹底分析〜インド編 その3.インドの指導者(知性)は、決して欧米に屈服はしない
前回は、独立後の経済政策の動きをみてみました。
インド経済が市場主義を強めて行く1990年代以降、その経済政策決定に深く係わってきたのが、現在のインド首相である、マンモハン・シン博士です。
(BRICs首脳会議。右からシン首相、胡錦濤・中国国家主席、メドベージェフ・ロシア大統領、ルラ・ブラジル大統領)
シン首相は、1932年生まれの77歳、ケンブリッジ大学を卒業し、オクスフォード大学で博士(Ph.D.)を取得している経済学者の顔をもっています。
シン首相は、欧州基準では、オックスブリッジのPh.D.という超エリート層です。そして、1970年代からの世界経済と欧米の対途上国政策を見続けてきた長老でもあります。
今回は、脱欧米という「新・世界秩序」への動きの中で、インドの可能性を探る意味で、シン首相に代表されるインド指導者(インドの知性)を紹介してみます。以下の3人です。
1.欧米の手の内を熟知しているマンモハン・シン首相(77歳)
2.ノーベル経済学賞もつインドの知性アマルティア・セン博士(77歳)
3.食糧グローバリズムを鋭く批判するヴァンダナ・シヴァ科学哲学博士・女史(58歳)
本文を読む前に、応援クリックを!
新しい潮流4 言葉それ自体が引力を持ち得ない時代
前回「新しい潮流3:社会不全⇒認識欠乏の蓄積」では、現在社会にはびこる社会不全は、涙や笑い、遊びなど従来からの解脱様式では解消できず、新しい認識によってしか解消されないのに、答え欠乏=認識欠乏が蓄積され続けるだけという社会状況を扱いました。
今回は、この認識欠乏がどんどん蓄積していく一方、社会不全が顕在化した2000年頃から起きた、小泉フィーバー、イチロー、ホリエモン、NWビジネス成功者、人間ウォッチングなどの現象に現される「人収束」と、メル友、ネット繋がり、サークル仲間の現象に現される「人収束」という新しい現象は一体何だったのか?どうして答え=構造認識に人々が集まってこないのか?を扱います。

写真はこちらからお借りしました。
続きはポチッの後で↓↓↓

CO2排出権市場ってどうなっている?2 排出権取引の仕組み

前回のエントリーでは、今月3日から三井住友銀行が個人向け国債に温室効果ガスの排出権を付けたものを販売しており、身近なところで排出権取引が浸透しつつあるということを紹介しました。今回は、排出権取引の仕組みについて京都議定書排出権を中心に調べてみたいと思います。
1997年12月に京都で開催された「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」において『京都議定書』が採択され、気候変動枠組条約における附属書Ⅰ国(後述)の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある排出削減の数値目標が設定されました。
そして、排出削減目標を達成するための補足的な仕組として市場原理を活用する京都メカニズム(下記の3つ)が導入されました。
①共同実施(JI) <京都議定書第6条>
②クリーン開発メカニズム(CDM) <京都議定書第12条>
③国際排出量取引(IET) <京都議定書第17条>
簡単に説明すると、
・『共同実施』とは、温室効果ガス排出量の上限が設定されている国同士が協力して、それらの国内において排出削減プロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量に基づいてクレジットが発行される
・『クリーン開発メカニズム』とは、温室効果ガス排出量の上限が設定されている国が関与して、排出上限が設定されていない国(途上国)において排出削減プロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量に基づいてクレジットが発行される
・『国際排出量取引』とは、温室効果ガス排出量の上限が設定されている国間での、排出枠・クレジットの取得・移転(取引)
今回は上記3つの京都メカニズムの実施の結果生じる排出権(クレジット)の取引の仕組みについて扱います。
興味を持たれた方、ぽちっと応援お願いします 
「市場は環境を守れない、社会を統合できない」シリーズ3〜「等価交換」の欺瞞

こんにちは。今日は「市場は環境を守れない、社会を統合できない」シリーズ3回目です。
これまでの2回は『環境』に焦点を当ててきました。
今や誰もが全人類的課題であると認識している環境問題と背中合わせで『市場拡大』という目的が存在している事、また『環境保護主義』の背景にはアメリカの支配層による周到な企てが存在していた事など、新聞、TVなどでは決して報じない内容を知ることが出来ましたね

さて今回は、現在の市場メカニズムの中でも常識化している『等価交換』という概念に斬り込んでゆきます

本文を読まれる前に ↓クリックお願いします

 いつも応援ありがとうございます
いつも応援ありがとうございます 
日本の税システムを考える−8 一般取引税で社会が変わる!?(5)
こんにちは〜 
日本の税制の抜本的転換を提言する「一般取引税を導入して夢のジパングへ」(馬場英治氏)を紹介するシリーズの第5回 
前回までの記事はこちら 
第1回
第2回
第3回
第4回
前回から引き続き、この税の導入による社会への様々な影響を、著者の馬場氏が考察した部分について紹介、検討してみましょう 
ランキングにご協力お願いします  ぽちぽち
ぽちぽち 
(ご協力ありがとうございます  )
)
BRICs徹底分析〜インド編 その2.インド独立後の経済と政治
前回のインド編 その1では、インドでソフト産業が伸びた要因を扱いました。
中国に次ぐ高いGDP成長率を維持し、今や世界経済を牽引しているといっても過言ではないまでになったインド経済は、どのようにして作られたのでしょうか?
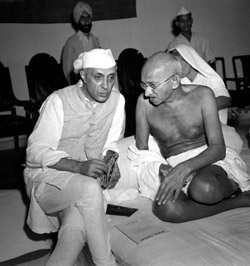
ネルー(左)とガンジー(右)
今後の世界経済を予測するためにも、インド経済の動向は注目されます。そこで、今回は独立後のインド史を、経済と政治を中心に振り返ってみます。
1.インド独立後の経済政策の歩み。社会主義的な経済政策から市場化政策への変遷
2.農業国家インドの危機。市場原理の色彩の強い「緑の革命」の導入
3.IMFは、国家資産を収奪する機関。IMF支援により一層市場化に巻き込まれていく
本題に入るまえに、いつものポチッとお願いします

新しい潮流3 社会不全⇒認識欠乏の蓄積

写真は
‘00年頃、私権統合の崩壊が決定的となり、潜在思念の源泉部が私権不全から社会不全へと大転換しました。しかし、答えがないので、潜在思念に増大していく社会不全を、必死に捨象している状態が続きました 🙁 
(詳しくは前回の記事『新しい潮流2 私権統合の崩壊と社会収束の潮流(’90・’00年代)』をご覧下さい  )
)
その社会不全はどうやったら解消されるのでしょうか
今回は、人類の不全とその解消様式を、時代をさかのぼって整理するところから始めます 🙄
ぽちっとお願いします 
CO2排出権市場ってどうなっている?

平成22年6月3日の毎日新聞の記事によると
三井住友銀行は2010年6月3日から、同行が販売するすべての個人向け国債に温室効果ガスの排出権を付ける。国債の購入者1人につき、二酸化炭素(CO2)100kg分の排出権を同行が取得。政府に無償譲渡し、日本のCO2排出削減にあててもらう。国債購入者が増えれば日本のCO2削減量が増える形で、同行は環境貢献をアピールするとともに、低金利で人気が低迷している国債の購入者のすそ野を広げたい考えだ。
とのこと。
私達の身近では、CO2排出権取引が静かぁに浸透しつつあるようです。
そういえば以前騒がれた排出権って一体どうなっているのでしょう?気になるあなたも気にしないあなたも、続きに行く前にランキング応援ポチっとよろしくね 

シリーズ「市場は環境を守れない、社会を統合できない」2〜環境保護主義が盛んになったのはなんで?〜
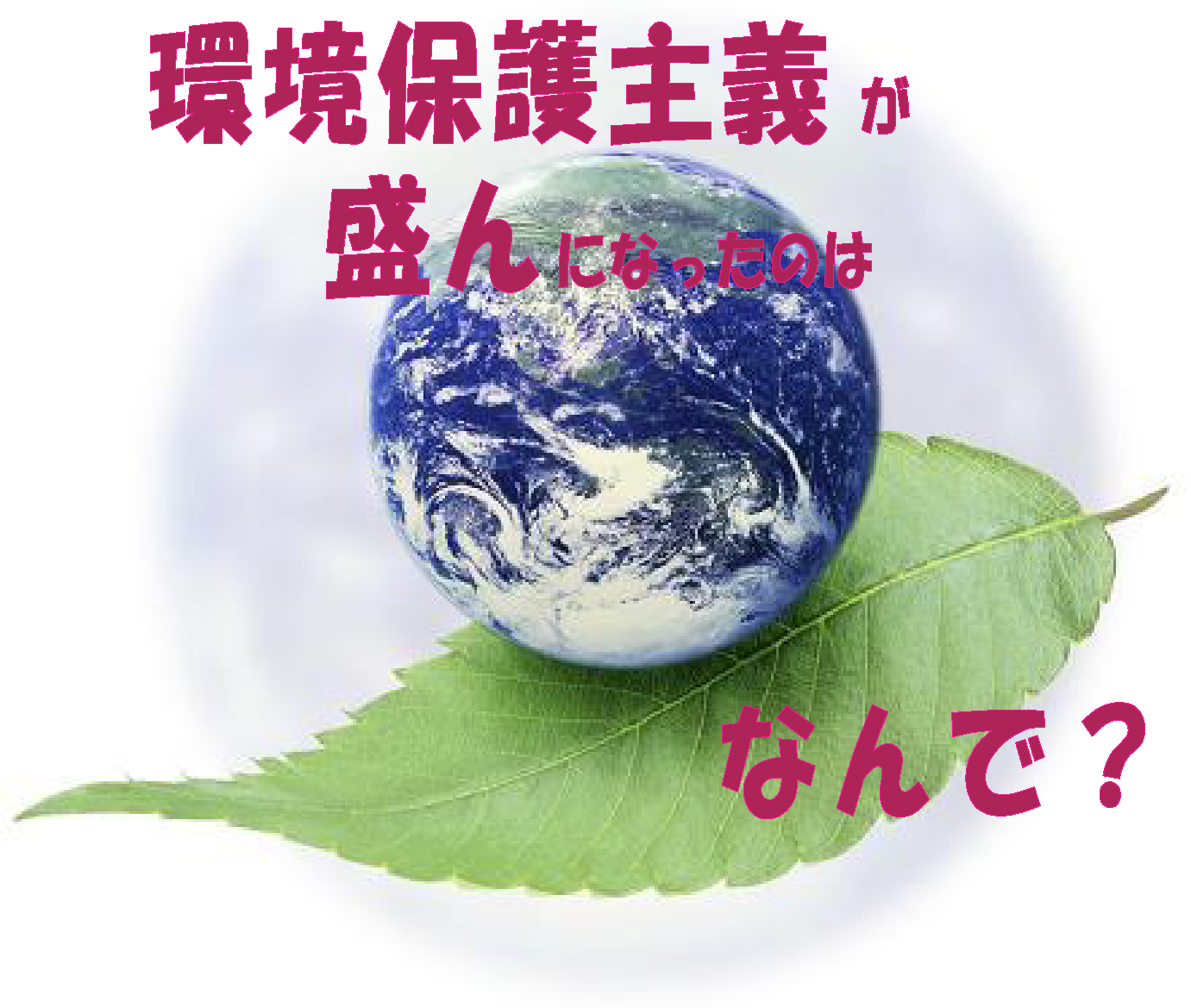
今回は、シリーズ第2回です☆先回は、環境問題を市場原理の観点から見てみました。
環境問題を意識させる言葉or映像は、日々の生活の中に溢れています。しかし、大掛かりなキャンペーンの数々は、私達にお金を浪費させる為の手段だったのです。まさに、欺瞞に満ちた世界が私達の周りには広がっているんですね。
今回は、環境問題という世界的なテーマがどの様に作られたのか見ていきます。そこには、ある研究所、さらには世界規模の組織が関係していたのです。今回の記事では、さらにそこから、環境保護主義の勢力が拡大する構造を明らかにします。
いつもありがとうございます。
『ユーロ発国家財政危機の行方』3.地域共通通貨「ユーロ」の弱点構造
前回6/11「小国ギリシャの危機がなぜユーロ危機につながったか?」に引き続き、「地域共通通貨「ユーロ」の弱点構造」について追求していきたいと思います。
今まで追及してきたテーマです。
・『ユーロ発国家財政危機の行方』 プロローグ
・『ユーロ発国家財政危機の行方』1.ギリシャ問題・PIIGS問題とは?
・『ユーロ発国家財政危機の行方』2.小国ギリシャの危機がなぜユーロ危機につながったか?

(ウィキペディア・欧州中央銀行から借りしました)
●ユーロ危機のおさらい。
小国ギリシャの危機が、ユーロ危機に繋がったのは、ギリシャを初めとするPIIGS諸国の国債をドイツ、フランスの金融機関が多額に持っているからである。もしPIIGS諸国がデフォルトをしてしまった場合、ユーロ中枢のドイツ・フランスの金融機関は忽ち苦しくなり、ドイツ・フランスも危機に陥り、最終的にはユーロ危機に繋がる。
今回は地域共通通貨「ユーロ」について、弱点はないのか?を追求してみます。
いつものブログ応援よろしくお願いします。