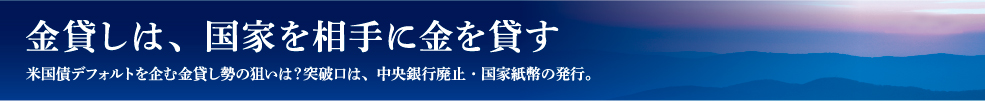2009-10-31
「経済学って、本当に正しいの?」5 〜市場における歪んだ計算式〜
いつもブログ記事を読んでいただいてありがとうございます。
経済学って、本当に正しいの?」シリーズの第5弾になります。
前回の第4弾では「何故これほど市場を絶対視するのか」に注目し
「不確実性の時代」とは人為的に仕組まれたものであるということがわかってきました。
今回のテーマの前に経済学の歴史(変遷)を少し復習してみます。
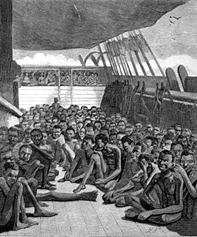
船に載せられて大西洋を渡る黒人奴隷

アヘン戦争戦闘図

その前にいつものようにバナーでの応援をお願いします。
アメリカの覇権、今後のシナリオ〜知財と資源〜
前回「アメリカ覇権、今後のシナリオ〜デフォルト構想」で紹介しましたように、世界を支配する権力=覇権には以下の4つがあります。
1.「武力」 2.「通貨」 3.「知財」 4.「資源」
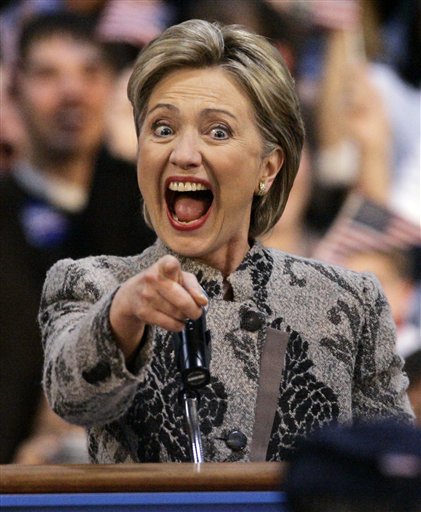
さて「武力」「通貨」に続きアメリカが獲得しようとする覇権を検証してみましょう。
まず「知財」=知的財産権について、アメリカは何を考えているのでしょうか?実は既に着々と手を打っているのです。同じくElectronic Journalさんから引用(一部補足)しました。
*以下引用
≪カーター政権≫
◎1982年/連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の創設
アメリカ合衆国全域における特許権侵害および特許の有効性に関する控訴事件を扱う。
≪クリントン政権≫
◎1988年/スペシャル301条の成立
貿易相手国の不公正な慣行に対して当該国との協議や制裁について定めた通商法301条の知的財産権についての特別版
◎1994年/TRIPS協定のGATTにおける成立
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の一部を成す知的財産に関する条約
◎1995年/中国の偽造CDの生産拠点の閉鎖
—————————————————————————————
米政府、とくに民主党政権が知的財産権の保護に熱心です。
なぜ、米国はこれほど知的財産権の保護を声高に主張するのでしょうか・・・?
*引用終わり
と続きの前にランキング応援ポチっとよろしくね 

『これからの消費はどうなる?』5〜新たな消費スタイルの萌し〜

先週は「お金を超える評価指標」としての“人数”について、その重要性も含めてお伝えしました。
今週は少し視点を変えて、リサイクルなどが孕む欺瞞性とは何かを押さえた上で、変わりつつある消費スタイルを見て参りましょう。
読む前にポチっとお願いします。 😛
「民主政権下で郵政民営化どうなる?」(4) デビッド・CIA・マスコミ VS 民主党・亀井の闘い
郵政民営化見直しへの動きが進んでいます。
「政府・与党は15日、今月26日召集予定の臨時国会に郵政民営化見直し関連法案を日本郵政グループの株式売却凍結法案1本に絞って提出する方針を固めた。
そのため郵政民営化見直しを最優先課題に据える国民新党は、基本法案に盛り込む予定だった(1)郵便局での郵便、貯金、保険の3事業の一体的な提供(2)金融2業の全国一律サービスの実施−−を閣議決定に持ち込む方向で調整を始めている。」
10月16日 毎日新聞 より
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドルに代わる通貨システムは?〜3.「戦争屋」の経済戦略は“ドル軟着陸”と“日本外し”?
 今回の記事では、前回記事に続き、次の国際通貨候補と目されるSDRを発行するIMFの実権を握るのは誰か?というテーマでアップする予定だったが、10月25日の朝日新聞に米国経済界の重鎮、ピーターソン国際経済研究所所長のフレッド・バーグステン(左の写真)のインタビュー記事が掲載されたので、まずはこれを紹介したい。今後の米国金融寡頭勢力の世界経済戦略および通貨戦略、とりわけ“戦争屋”の意向を読み解く上で重要だと思われるからだ。
今回の記事では、前回記事に続き、次の国際通貨候補と目されるSDRを発行するIMFの実権を握るのは誰か?というテーマでアップする予定だったが、10月25日の朝日新聞に米国経済界の重鎮、ピーターソン国際経済研究所所長のフレッド・バーグステン(左の写真)のインタビュー記事が掲載されたので、まずはこれを紹介したい。今後の米国金融寡頭勢力の世界経済戦略および通貨戦略、とりわけ“戦争屋”の意向を読み解く上で重要だと思われるからだ。
いつも応援ありがとうございます。
経済破局を突き抜けていく道標 〜潮流5:失われた40年


前回記事『潮流4:輸血経済(自由市場の終焉)』では、
①豊かさが実現された’70年以降、需要が頭打ちになって自由市場は縮小過程に入ったこと。
②市場が縮小している以上、いくら国が資金をつぎ込んでも実態経済が回復することはなく、余ったお金が投機市場に流れ込んでバブル化するだけであること。
を学びました。
今回は、’70年以降の40年間、市場縮小という現実から目をそらし、無為無策のまま景気対策と称して国の借金を積み上げたのはなぜなのか? 本当はどうすれば良かったのか?を扱います。
応援おねがいします♪
ありがとうございます。


10/18なんでや劇場レポート2〜私権追求に代わる集団の目標は周りの充足、そして男女の共認の輪が認識収束の母胎〜
10月18日になんでや劇場が開催されました。
今回は、「私権に代わる集団の目標は?社会の最基底である男女関係は?」
の2本のダイジェストと、後半部分の男女関係についての図解を紹介します♪
いつものようにポッチお願いします!
10/18なんでや劇場レポート1〜図解・暴走する特権階級と下層階級〜
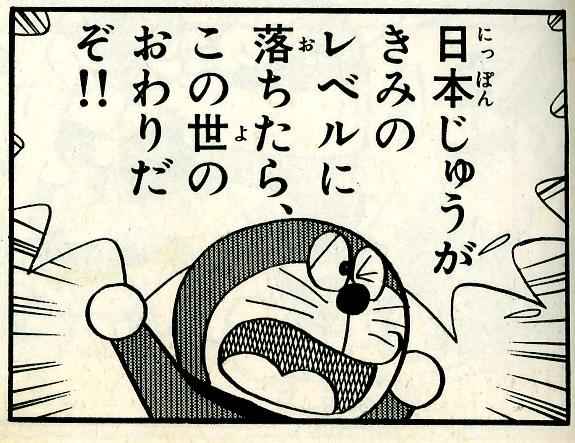
はじめまして、ハシヒロといいます:D 数週間前から、「金貸し」ブログのメンバーに参加させていただきました。今後ともよろしくお願いします 
さて、去る10月18日になんでや劇場が開催されました。
今回の劇場のテーマは、
 テーマ①:圧力低減下で好き放題に振舞うニセ者=暴走する特権階級と下層階級、及び民主党政権
テーマ①:圧力低減下で好き放題に振舞うニセ者=暴走する特権階級と下層階級、及び民主党政権
テーマ②:女規範・男規範の共認から、男女共認の輪を広げていく
前半の議論では、テレビの官僚も、私達の身の回りの人も、暴走しまくる人々の意識構造を構造化し、彼らの位置づけを明確にしました。後半では、認識形成の最初のかたちとは?そして新認識への必要性に向かうのは一体どのような構造なのか?に焦点を当てた議論で、気づきと驚きの連続でした 
今回は、なんでや劇場の前半で行われた内容をダイジェストで紹介し、そしてその内容を図解化したものをぜひみなさんに見ていただきたいと思います。
それでは、まずはポチッとお願いします 
『経済学って、本当に正しいの?』4 〜何故これほど市場を絶対視するのか〜
『経済学って、本当に正しいの?』シリーズの第4弾
前回の第3弾では「市場拡大に必要なもの」に注目し、『市場拡大には国家統合における不安定要素が不可欠である』という基本原理があることを紹介しました。 😉
国家や国民は「豊かさ実現」、金貸しは「金儲け」という思惑から、目標共認として「市場拡大」は一致しています。
でも一方で、安定した社会秩序を望む国家や国民と、市場拡大には不安定要素が不可欠であることに気付いている金貸しとでは矛盾を孕むこととなります。
この矛盾をいかにして誤魔化し、正当化する屁理屈を作り出して行ったのか?また不安定要素って何?という疑問に答えてくれる引用文紹介してみたいと思います。 
その前にいつものように  ポチ
ポチ  ポチ
ポチ  ポチ
ポチ  っと応援の方をお願いします。
っと応援の方をお願いします。
『これからの消費はどうなる?』4〜お金を超える評価指標〜

前回、るいネットの超国家・超市場論を紹介しましたが、その中で、もはや皆の意識の中では物的豊かさの追求から、「必要か否か」という判断の土俵が登場していることを伝えました。
そしてこの「必要か否か」の判断の土俵が現れることによって、国家や市場も変質し、お金という評価指標をも変わっていくんです。
その中身とは・・
読む前にポチっとお願いします。