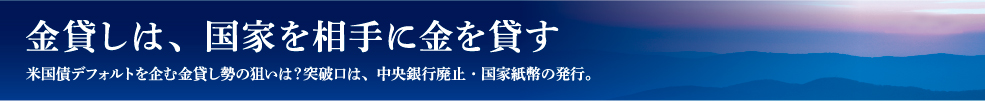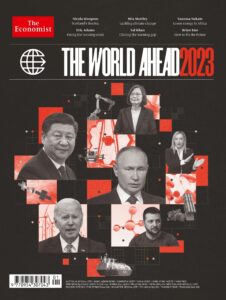見えない戦争 ~異次元緩和政策から異常に膨れ上がった投機経済を読み解く~
今回扱うのは・・・「そもそも異次元緩和とは?!」
前回は世界的に「金利・株価・資源」のどれもが高水準という、経済学の常識ではありえない状況について押さえた。しかし、日本に絞ってみれば「株価・資源」は依然高水準なものの、「金利」だけは各国と比較しても異常に低い水準にとどまっている。
この低金利の所以は10年以上日本政府が続けている「異次元緩和」によるもの」。少し遡って押さえていく。
- 異次元緩和とは何?なぜ始めた?
異次元緩和の中身は大きく2つ。「紙幣を大量に刷り市場にばら撒くこと」と「ゼロ(マイナス)金利」。
続きを読む "見えない戦争 ~異次元緩和政策から異常に膨れ上がった投機経済を読み解く~"
ドル支配・SWIFT制裁の濫用が新しい国際通貨システム構築を加速

Mohamed HassanによるPixabayからの画像
ロシア・ウクライナ問題に関して、欧米諸国が中心となって2022年2月よりロシアへの経済制裁を発動させている。その一つとして、ロシアの金融機関を国際的決済網であるSWIFTから遮断する措置が取られている。
続きを読む "ドル支配・SWIFT制裁の濫用が新しい国際通貨システム構築を加速"
金融の構造① 銀行システム(中央銀行+銀行)と債務マネー
現代の経済は、金貸しが金を貸す債券経済→債務マネーで運営されている。
今後の金貸しVSロシアなどの情勢予測のため、金融の原理的な構造から把握してみる。
続きを読む "金融の構造① 銀行システム(中央銀行+銀行)と債務マネー"
世界のインフレの原因~経済の不安定が長期化する構造的理由
イギリスの政治経済誌
『エコノミスト(The Economist)』
をご存知でしょうか。
毎年恒例となる『エコノミスト』の『世界はこうなる(The WorldAhead』2023年版が発刊されました。
ロスチャイルド系の経済紙として有名な、この『エコノミスト』誌の表紙は、翌年を予言すると言われています。
しかし、これまでを振り返ってみると、それは予言ではなくて、
実は、新世界秩序(New World Order)による年度計画を表していることがわかるとも言われています。
2023年度版の表紙は以下のようなもの。
The Economist: The World Ahead 2023
表紙からの考察は、
世界中の研究者があれこれ予測してますので、
関心があれば他のネットを覗いてみてください。
今回、ご紹介するのはエコノミストのHP(英語版)に掲載のある、the world ahead2023の記事より、「2023年に世界的な景気後退が避けられない理由~世界は地政学、エネルギー、経済のショックで動揺している~」を要約、図解化したいと思います。
続きを読む "世界のインフレの原因~経済の不安定が長期化する構造的理由"
中国のゼロコロナ政策見直しで、世界は安定に向かえるか?
中国のゼロコロナ政策は、世界経済に大きな影響を与えています。さらには、ロシアのウクライナ侵攻という大きな問題が発生している中で、中国の内政が混乱すれば、中国が台湾に武力侵攻を仕掛ける恐れもあります。中国のゼロコロナ政策は今後の世界情勢にも大きくかかわってきます。
中国は何故ゼロコロナ政策を重視し、転換が困難になっているのか、今後どうなるのか追求してみました。
続きを読む "中国のゼロコロナ政策見直しで、世界は安定に向かえるか?"
ロシアの新通貨構想/セルゲイ・グラジェフの金融システム
8日、習近平が突如サウジを訪問、石油取引を人民元を決済通貨として使うことを合意。
中露によるドル覇権解体は着々と進んでいる。今年6月の第14回BRICSサミットでプーチンが発表した新たな国際基軸通貨構想。
~中露主導の拡張BRICSによる経済圏構築、新国際決済通貨(バスケット通貨)導入へ~ロシアの通貨構想の中核立案者であるセルゲイ・グラジェフに関する記事について、
以下紹介します。
続きを読む "ロシアの新通貨構想/セルゲイ・グラジェフの金融システム"
日本はエネルギーを自給できるか
生活、社会発展をさせるために、エネルギーの存在は欠かせません。
しかし、近年の人口増加や経済発展に伴い化石エネルギーの消費量が急増し、エネルギーの枯渇がさらに早まっていることが大きな問題となっています。
また、特に日本は国内のエネルギー資源が非常に乏しく、エネルギー自給率が非常に低いことが特徴です。
海外からの輸入に依存していることが現状としてあります。
そもそも、本当に日本に資源はないのでしょうか?
見えない戦争 ~不整合な金融政策を読み解く2~
前回の投稿では、改めて世界情勢を学ぶ意義・求心構造を捉え直した。
シリーズ「見えない戦争」では、現在の世界経済の動きと、その背後にある政策・意思決定がどう行われているかを読み解いていくことをテーマに進める。
●さっそく今回扱うのは…
「金利(日本を除く)・株価・資源のいずれもが同時に高水準なのは何で?」
続きを読む "見えない戦争 ~不整合な金融政策を読み解く2~"
ロシア、中国、米欧・・・世界情勢の俯瞰
ウクライナ戦の継続、中国はゼロ・コロナなど、現在起こっていることのつながりから現在の世界情勢を大きく俯瞰、今後の見通しを考えた。
日本の米国債離れが始まっている?下半身は、BRICS入りか?
最大の米国債保有国、日本と中国の米国債離れが始まっている。