70年貧困の消滅で、市場は縮小過程に入った−その8「女子大生の意識潮流に見る可能性」
◎前回、シリーズ第7回では‘70年豊かさ実現で市場は縮小に向かっているにも拘わらず、野放図な資金供給でバブルを引き起こし、それを煽りかつ放置した政治家、官僚、財界トップ、学者、マスコミ人の、無能さを見てきました。
第8回の今回は、「豊かさ」実現した現在社会での若者の意識潮流に見ていきます。

豊かさ時代の女子大学生
クリック御願いします
○豊かさが実現した、現在若者の意識潮流を紹介した記事がありましたので紹介しましょう(記事は「女子大生の意識潮流にみる可能性」から)
神戸女学院大学・内田樹研究室が女子学生2年生にゼミ面接のため50人ほどと話したそうです。
衝撃的です。ここまで世界は変化しています。(中略)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
お教えしよう。
彼女たちが注目している問題は二点ある。
一つは「東アジア」であり、一つは「窮乏」である。
東アジアへの関心の主題として挙げられたものは「ストリートチルドレン」「麻薬」「売春」「人身売買」「児童虐待」「戦争被害」「テロリズム」「少数民族」などなど。

これらは、「法治、教育、医療、福祉、総じて人権擁護のインフラが整備されていない社会で人はどう尊厳ある生を生きることができるか?」という問いに言い換えることができる。
そう言い換えると、「危機モード、窮乏モードを生きるためにどうすればいいのか?」という彼女たちの関心の射程がある程度見通せる。
若い女性の「窮乏シフト」の徴候は、私が面談した50人弱の中に「消費行動」を研究テーマに挙げた学生が一人もいなかったことからも知られる。

☆下のグラフはサンケイリビング社が今年7月にOL1093人に行った意識調査「「OLマーケットレポート」」のうち「1年前と比較して、消費意欲どうなりましたか?」という質問への回答です。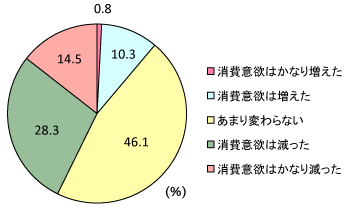 アンケートの編集者は「変わらない」と「増えた」層が60%近くいるので、まだまだ旺盛な消費があるという分析をしていますが、私はむしろ「減った」「かなり減った」層が42%もいるほうに驚きを覚えます。アンケートに答えたのは平均年齢約35歳で65%近くが正社員であり、比較的金銭的余裕のある層と考えられます。不況の影響はあるにせよ、この結果からは女性の消費意識が急激に減退しているという印象を拭えません。
アンケートの編集者は「変わらない」と「増えた」層が60%近くいるので、まだまだ旺盛な消費があるという分析をしていますが、私はむしろ「減った」「かなり減った」層が42%もいるほうに驚きを覚えます。アンケートに答えたのは平均年齢約35歳で65%近くが正社員であり、比較的金銭的余裕のある層と考えられます。不況の影響はあるにせよ、この結果からは女性の消費意識が急激に減退しているという印象を拭えません。
これまでは毎年「ブランド」とか「ファッション」とか「アート」とか「美食」とか「女子アナ」とかいう消費生活オリエンテッドな研究テーマを掲げる学生たちが相当数いたのであるが、今年はみごとにゼロである。
「人はその消費生活を通じて自己実現する」という80年代から私たちの社会を支配していたイデオロギーは少なくとも20歳の女性たちの間では急速に力を失いつつある。
 画像リンク「農ギャル」
画像リンク「農ギャル」
「お金さえあれば自己実現できる」「自己実現とは要するにお金の使い方のことである」というイデオロギーが優勢でありえるのは、「右肩上がり」幻想が共有されている間だけである。
「お金がないから私は“本来の私”であることができません」というエクスキューズはもちろんまだ私たちの社会のほとんど全域で通用している。
その現実認識には「だからお金をもっとください」という遂行的言明が続く。
その前段にあるのは、「私たちの不幸のほとんどすべては『金がない』ということに起因しているから、金さえあれば、私たちは幸福になれる」という「金の全能」イデオロギーである。
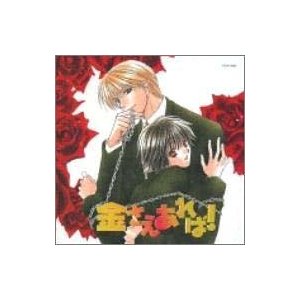 「金さえあれば!」画像リンク
「金さえあれば!」画像リンク
このイデオロギーにもっとも深く毒されているのはマスメディアである。
メディアはあらゆる機会に(コンテンツを通じて、CMを通じて)視聴者に「もっともっと金を使え」というメッセージを送り届け、その一方で非正規労働者や失職者がどれほど絶望的な状況であるかをうるさくアナウンスして「消費行動が自由にできないと人間はこんなに不幸になるんですよ」と視聴者を脅しつけている。
 画像リンク
画像リンク
そして、メディアの当事者たちは自分たちがそのようなイデオロギー装置の宣布者であることについての「病識」がない。
けれども、若い女性たちはそろそろこのイデオロギーの瀰漫に対しての「嫌厭感」を持ち始めている。だって、そのイデオロギーを受け入れたら、消費生活が不如意である彼女たちは今「たいへん不幸」でなければならないはずだからである(現に手元にお金がないんだから)。
だが、それは彼女たち自身の生活実感とは「違う」。
「ストリートチルドレン」より私たちはずっと恵まれた環境にいる。
その私たちは彼らに何ができるか。
そういうふうに考える人が(続々と)登場してきた。
彼女たちは「自分より豊かな人たち」に向かって「あなたの持っているものを私に与えよ」と言うのを止めて、「私より貧しい人たち」に「私は何を与えることができるか」を問う方向にシフトしている。
私はこのシフトを健全だと思う。(中略)若い女性たちが「自分たちには何が欠けているのか」を数え上げることを止めて、「自分たちが豊かにもっているものを誰にどんなかたちで与えることができるのか」を考える方向にシフトしたのは、彼女たちの生物学的本能が「危機」の接近を直感しているからだと私は思う。
このシフトは世を覆う「金の全能」イデオロギーの時代の「終わりの始まり」を告げるものだろうと私は思っている。
////////////////////////////////////////////////////////////////
とうとう変わった!
もう若い女性は消費主体ではない。☆今の若い女性は、結婚(恋愛)相手の条件としてかつて高度成長時に言われた、「三高」(学歴、収入、身長)志向は皆無となり、「三低」〜「低姿勢(レディーファースト)」「低リスク(公務員などのように安定した職業)」「低依存(家事などを女性に依存しない)」といわれます。(リンク)この「三低」志向は、かつての豊かさ欠乏から発した「3高」幻想が剥げ落ちた後の、彼女達の男に対する現実的な醒めた期待が感じ取れます。
例えば、
○出世志向の恋人はイヤ。『朝日新聞平成22年10月18日朝刊記事、全国の会社員618人に聞いた。恋人にしたくない人としては、男女とも「役職や昇進にこだわる出世志向タイプ」』 しかし今後、社会の不全感がますます亢進するに従い、女性たちは「三低」と言ったレベルに満足出来るはずは無く、本来の男と女の役割りを求めて探索が始まる予感があります
○転換期の女たち。リンク
○女性の二つの可能性。リンク
○仕事をする上で重要な、「男であること」「女であること」。<>リンク
○借金してでも「社会貢献」にハマる若者たち。リンク
○消費にも「正義」が求められる時代——これからの「消費」の話をしよう。リンクトラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kanekashi.com/blog/2010/10/1421.html/trackback
コメント1件
Comment
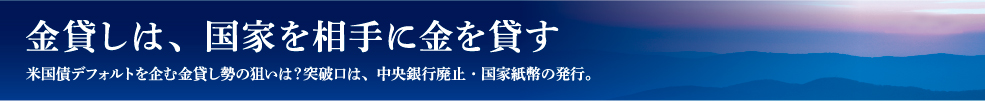


ミュウミュウ 2013 靴