中国製冷凍食品事件をのぞいてみれば・・・
前回の投稿 で明らかにしたように毒餃子事件を起こした直接の責任者はJTフード、双日、生協で、日本のスーパー等の量販店やコンビニを含む外食産業です。
つまり、中国食品の急増や今回のような事件を招いた本当の張本人は、家庭食を放棄しつつある私たち一人一人だともいえます。
長江(揚子江)の水質汚染
中国食品問題はすでに、日本の問題なのです。我々は当事者なのです。
もっと事実を知り、考え、答えを出して世論形成しなくては一行に改善されていかないのです。
ということで中国の現状を調べてみました。
すると日本の「食」が中国に依存することの危険性が見えてきました。
続きを読んで中国の農業の現状を知ってください。
ブログランキングアップに協力願います。



■中国の農業と環境問題。
中国は世界人口の20%を占めながら、水資源は世界全体のわずか7%しかありません。
中国の660の都市の半分以上が水不足に苦しんでおり、1億6千万人に影響を及ぼしています。
また都市の90%の地下水、河川、湖沼の水の75%が汚染されており、水質汚濁の広がりのため、
毎日7億人が汚染された飲料水を飲んでいます。
農業をするには、農業ができる環境が必要です。
しかし、中国では、農業を阻む要因が沢山あります。
土地の疲弊、そして砂漠化、、90年代には国土の40%で土壌の浸食が発生。
砂漠化の影響を受けた土地は2億6200万ヘクタールにも上ったと言います。
過剰な干害による土地の塩害に襲われた耕地は700万〜800万ヘクタールに達し、
90年代に入ってから耕地面積は年間40万ヘクタールの割合で減少。
途方もない規模で耕地が失われています。


山東省の揚子江河口 黄河のオイルボール
■中国の農業の最大の問題は、水 。
あれだけ広大な土地なんですが、水が不足しているんです。
しかもその水が工場排水や農業排水などでひどく汚れています。
中国の黒龍江省では、川の水は重金属汚染でとても使えたものではなく、地下水に完全に頼っている、とのこと。
乏しい地下水だけに頼ることは、水の必要な米作りにとってものすごく負荷がかかります。
それに、水田の土が固く水はけが悪いのでイネの根に対して、水(酸素)が十分行き渡っていない。その結果、水不足による病気(イモチ病等)が広がり、強力な農薬が、大量に使われるという結果になります。
こんな所でどうして米を作ろうというのでしょうか。
なぜ日本はこんな所の米を輸入しようとするのでしょうか。
このような外国の事情など、知ろうとしない日本の役人や輸入業者の人達が、机上の計算だけで、
農産物を輸入しようとしている。
こんな滑稽な図は、もう終わりにしたいものです。
■中国の農民は作っているものを知らない。
米については、いま述べたような事情ですが、ホウレンソウやゴボウなどは、じつは中国人は食べないんです。あくまでも日本向けに、日本の企業などが開発したもの。
自分で食べたこともない野菜を、海の向こうの日本人の健康のことを思いながら、はたして安全に作ることなどできるのでしょうか。
あんな水不足の地で、何も知らされずに、米や野菜を黙々と作らされている中国の農民たちが哀れ田と思いませんか。
皆さん、ちょっと考えてもみて下さい。
自分で食べたこともない作物を作る。
味も香りも栄養価も、何も知らない人が、外国人のためだけに作物を作る。
中国の農民が、自分で食べたこともない野菜を、日本人のためにせっせと作る現実。
こんな滑稽なことって、ありますか。
こんな危険なことって、ありますか。
これでは作るほうも、食べるほうも、お互いが不幸じゃありませんか。
■以上、中国の農業の現状を調べてみましたが、
日本の「食」が中国に依存することの危険性が見えてきたでしょうか。
現在の日本は「食」に限らず「電化製品」「衣類」など、生活用品の約50パーセントが中国製と言う調査もあります。
日本は環境汚染の進んだ中国に支えられた社会なのです。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kanekashi.com/blog/2008/04/517.html/trackback
コメント9件
匿名 | 2008.08.02 15:11
外貨準備高のグラフを見ると朝鮮特需と呼ばれる1950‐1953の間にはまったく伸びが無く、貿易赤字が解消された後もほぼゼロ、1970年以降にやっとプラスに転じています。
これはなぜ?
orimex | 2008.08.02 23:59
コメントありがとうございます。
>s.tanaka
>1ドル=360円で景気拡大すると、どうして貿易収支が悪化するんですか?
これについては、詳細を今後確認していくつもりですが、引用にある「1ドル=360円を維持するような経済運営」というのがポイントだと思います。
2つ目の引用からも、高度経済成長を牽引していたのは、「内需」であることがわかります。つまり、内需に対する国内生産量を増やせば、海外からの原材料輸入が進み、輸出<輸入となって、円安=ドル高が進みます。
当然、そのままだと1ドル=400円、500円になりますが、当時は1ドル=360円を維持することが命題だったため、国内景気を冷やしてまで輸入量を減らし、強引に円高を進める政策が必要だったようです。
>匿名さん
外貨準備高のグラフを見ると朝鮮特需と呼ばれる1950‐1953の間にはまったく伸びが無く、貿易赤字が解消された後もほぼゼロ、1970年以降にやっとプラスに転じています。
これはなぜ?
これも詳細は要確認ですが、予測としては、やはり、日本製品の国際競争力が低かったからではないでしょうか。1970年代までは輸出<輸入で、外貨が全く溜まらなかったのではないかと考えられます。
これは、国際競争力が付き始めた1970年代頃からは輸出>輸入となって、外貨準備高が逆転構造になっていることからも予測できます。(国内需要が冷え込んだ可能性もありますが)
近年の日本は、輸出超過で円高を押さえるために、ドル買いを進めた結果、膨大な外貨を抱える構造になっていますので、やはり輸出と輸入の関係はポイントではないでしょうか。
是非、次回以降の投稿で解明していきたいと思いますのでお楽しみに!!
mihori | 2008.08.03 2:28
「外貨」獲得の重要性って全然分かってなかったです(@o@;
確かに、何かを輸入しようとしたら、「外貨」って必要になりますもんね☆
あと、「朝鮮特需」の時もずっと貿易赤字が続いていたというのも
びっくりでした。
次回以降も楽しみにしています☆
orimex | 2008.08.04 1:46
>mihori
コメントありがとうございます。
>「外貨」獲得の重要性って全然分かってなかったです(@o@;
あと、「朝鮮特需」の時もずっと貿易赤字が続いていたというのもびっくりでした。
実は私自身も今回このテーマで勉強し直して分かったことなんです(@o@;
今回の追求で、高度成長期の状況が少しづつ繋がるようになってきましたので、次回以降の投稿も楽しみにしていて下さいね。
そして、また気付き or つっこみコメントあればよろしくお願いします。
バーバリー | 2012.10.18 9:12
今日は〜^^またブログ覗かせていただきました。よろしくお願いします。
匿名 | 2013.04.19 3:38
1ドル=360円だったらむしろ価格競争力はあがるのでは?
というか朝鮮特需で外貨稼いだのに、グラフでは増えてなくないですか? あなたの言う外貨とはドルだけなんですか?中国に輸出したいなら中国の通貨が必要です。
朝鮮特需で得たのはドルだけですよね?アメリカに武器や兵器を売ったんですから。
これでは外貨を得たとは言えないのでは?ましてやアメリカにしか輸出する事しかできないのに(ドルを得ただけでは)、高度成長なんて迎えられますかね?
paul smith bag | 2013.10.24 17:45
ポールスミス 財布 ハート
spain hermes | 2014.02.01 5:37
hermes outlet florida 金貸しは、国家を相手に金を貸す | 戦後日本の高度経済成長を検証する NO.3 〜朝鮮特需による外貨獲得〜
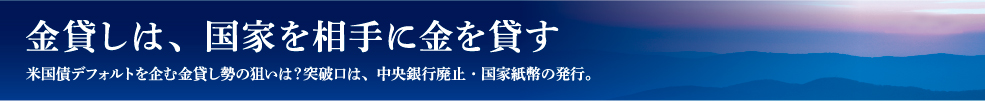


高度成長期の間も、日本は貿易赤字続きだったとは意外でした。
ところで、2つめの引用の中に書いてあるんですけど、
1ドル=360円で景気拡大すると、どうして貿易収支が悪化するんですか?