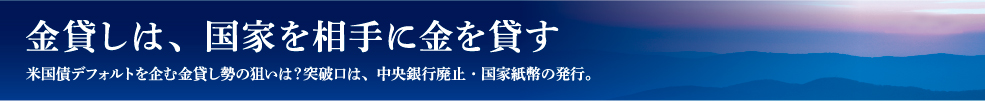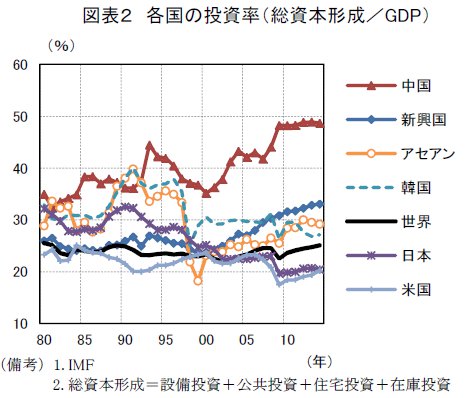金貸しが中国を見捨てる?

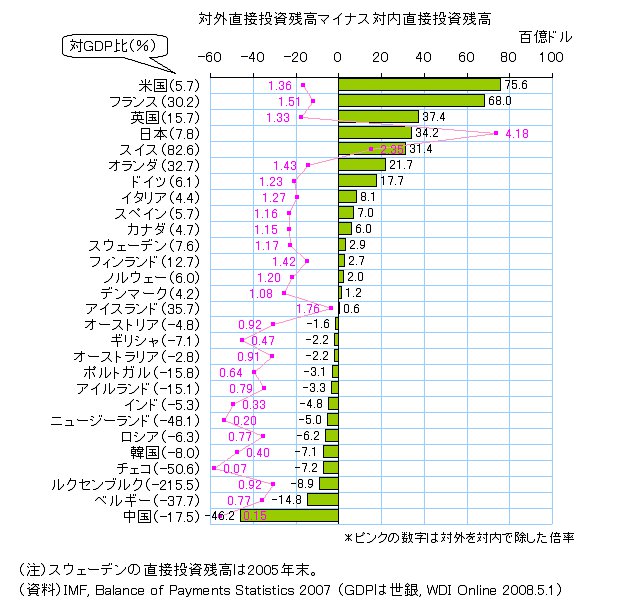
★国際金融資本が中国を見捨てる日
(略)日本には、「ある強固な信念」をもっている人たちがいます。
「強固な信念」とは?1、アメリカを支配しているのは、「国際金融資本」である。
2、中国を育てたのはアメリカを支配する「国際金融資本」である。
3、「国際金融資本」と中国の関係は、「国際金融資本」が上、中国が下である。(つまり、中国は、「国際金融資本」のいうことを全部聞く。)4、「国際金融資本」は「国境を超越する」が故に、「どの国が覇権
国家でも構わない」。5、「国際金融資本」は、アメリカを見捨て、中国を覇権国家にする
ことを決めた。6、だから、アメリカの未来は暗く、中国の未来は明るい。
いろいろバリエーションはありますが、基本はこんな感じだろうと思います。実際のところどうなのでしょうか?この問題に答えを与えてくれるのがこちらの本です。↓
(詳細は→ https://hec.su/bWqL )
副題は、
「秘密裡に遂行される『世界覇権100年戦略』」といいます。一見「陰謀論かな?」と思えるでしょう。ポイントは、「書いている人」です。著者のマイケル・ピルズベリーさんは、・アメリカ国防総省顧問。
・ハドソン研究所中国戦略センター所長。さらにアメリカの政策に大きな影響力をもつ・外交問題評議会・国際戦略研究所のメンバーである。さらに、この本で暴露しているのですがピルズベリーさんは、24歳のときから・アメリカのスパイ
として働いてきた。そして、この本は、「国家機密が漏えいしないよう、CIA,FBI、国防総省による査読を受けた」とあります。つまり、CIAもFBIも国防総省も、本の作成に協力している。この本を読めば、「米中が裏でベッタリひっついていたこと」が事実であることはっきりわかります。詳しくは本を読んでいただくとして、ここでは例をあげておきます。
▼「クリントン・クーデター」の衝撃
皆さんご存知のように、米中関係が劇的に改善したのは、70年代はじめです。当時は、アメリカとソ連の「冷戦時代」。しかも、アメリカは、ソ連におされ気味だった。ニクソンとキッシンジャー大統領補佐官(当時)は、「ソ連と対抗するために中国との関係を改善しよう」と決意します。当時まだ20代だった著者のピルズベリーさんは、「米中が和解するとソ連はどういう反応をするか?」に関する情報を集め、ニクソンとキッシンジャーの決断を後押ししました。こうして、「ソ連に対抗するため」という名目で米中はひっついた。
そして、トウ小平は、アメリカ(と日本)から、もらえるものを全部もらい、「奇跡の経済成長」を実現します。だから、「アメリカが中国を育てた」のは、そのとおりなのですね。しかし、米中関係に、大きな危機が訪れました。一つは、1989年の「天安門事件」。もう一つは、1991年末の「ソ連崩壊」と「冷戦終結」です。米中和解の論理は、「ソ連と対抗するため」でした。では、ソ連がなくなった今、「なぜ独裁国家の中国と仲良くするの?」という疑問が、当然アメリカ側からでてきました。そして、アメリカに「反中」の大統領が誕生します。なんと、クリントンでした。<大統領選のさなかには、「ブッシュ大統領は、北京の肉屋を甘やかしている」と攻撃した。クリントンが大統領に就任するとすぐ、国務長官のウォーレン・クリストファーは、上院外交関係委員会でこう宣言した。「わたしたちの政策は、経済力の強化と政治の自由化を後押しして、中国における共産主義から民主主義への広範で平和的な移行を手助けすることだ」>(140~141p)クリントンは、「中国もソ連のように『民主化させよう!』」と宣言していた。これはもちろん、中国共産党にとって、きわめてまずい事態でした。で、中国はどうしたか?
アメリカ政権内に、「親中派グループ」を形成し、クリントンの対中政策を「変える」ことにした。ピルズベリーさんによると、中国に取り込まれた人物の中には、
国家経済会議議長ロバート・ルービン、
財務次官ローレンス・サマーズなどが含まれていた。ルービンは、元ゴールドマンサックスの会長で、後に財務長官になった。(いわゆる「国際金融資本」の「大物」と呼べるでしょう。)サマーズは、ハーバード大学の経済学者で、ルービンの後に財務長官になった。「親中派グループ」は、政治家の味方を増やしていきました。そして、何が起こったのか?
<ついに1993年末、中国が現在、「クリントン・クーデター」と呼ぶものが起きた。中国に同調する面々が大統領に反中姿勢の緩和を認めさせたのだ。クリントンがかつて約束したダライ・ラマとの新たな会談は実現しなかった。対中制裁は緩和され、後に解除された。>(143p)驚くべき事実です。
中国はなんと、アメリカの外交政策を180度転換させることに成功したのです。ここまでで、米中関係についてわかることはなんでしょうか?1、中国を育てたのは、確かにアメリカである。2、しかし、ソ連崩壊で、アメリカは中国と和解しつづける意味を失った。3、それで、米中関係は悪化していた4、しかし、中国はロビー活動により、米中関係を好転させることに成功した
米中和解、アメリカ側のロジックは、
・1970~1991年 = ソ連に対抗するため
から
・1993年~ = 世界一の巨大市場中国で儲けましょうに変わりました。誰でも「儲けたい」ですから、アメリカ側のロジックも理解できます。▼なぜ国際金融資本は、中国が「覇権国家」になるのを容認しないのか?
とはいえ、「中国は、国際金融資本のいうことをいつまでも聞きつづける」、だから、「中国が覇権国家になっても、別に構わない」というのは違うと思います。なぜでしょうか?
「国際金融資本」は、「軍事力」をもたないからです。
この世界、主なパワーの源泉は、「金力」と「軍事力」です。
国際金融資本は、「金」をもっている。そして、覇権国家アメリカの政策を動かすことで、事実上「軍事力」ももっているともいえます。しかし、もしアメリカが没落し、中国が覇権国家になったらどうでしょうか?つまり、軍事力で中国がアメリカを圧倒したらどうでしょう?この時、中国が、「国際金融資本」のいうことを聞く理由はないのです。「儲けたければ、中国のいうことを聞け!」となるに決まっています。つまり、「軍事力」の裏付けがなくなった「国際金融資本」が中国を支配しつづけることはできないのです。(そうなれば、儲けつづけることも無理。)ですから、「国際金融資本は国家を超越する」というのは「相対的真実」にすぎません。ロスチャイルド家の後ろには、覇権国家イギリスがいました。ロックフェラー家の後ろには、覇権国家アメリカがいる。それが、彼らのパワーの源泉なのです。
▼国際金融資本が中国を見捨てる日
というわけで、私は、「国際金融資本は中国が覇権国家になるのを容認している」という信仰をもっていません。彼らが中国を育てたのは、「儲けるため」。
中国で儲けられなくなれば、当然「中国を見捨てる」と思います。そして、実際欧米の「国際金融資本」は中国を見捨てつつあります。夕刊フジ11月25日付<「中国売り」「韓国売り」が止まらない 欧米大手金融が撤退の動きを急加速>を見てみましょう。<かつては高い成長率を背景に、欧米の金融機関や投資家が積極的な投資を行っていた中国だが、経済の失速もあって、いまやマネーは逆流している。米紙ウォールストリート・ジャーナルは、米シティグループが、広東省の地方銀行、広発銀行の株式20%の売却に向けて協議していると報じた。シティは2006年に企業連合に加わり広発銀行を買収、当時の取得額は約6億2000万ドル(約760億円)だったが、シティが目指す売却額は明らかになっていない。>シティが、中国地銀の株を売却するそうです。シティだけじゃないですよ。↓<米経済メディアのブルームバーグによると、ドイツ銀行も北京にある商業銀行、華夏銀行の持ち分35億ドル(約4300億円)を売却する可能性を示唆しており、欧米の主要金融機関で、中国の大手銀行に大きな持ち分を持つのは、交通銀行に出資する英HSBCホールディングスだけになる。>(同上)ドイツ銀行も売却するそうです。
そういえば、冷戦終結後中国に取り込まれたルービンさん(前述)は、ゴールドマンサックスの元会長です。中国の発展に大きく貢献したゴールドマンは、どうなのでしょうか?↓<シティやバンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス・グループなどが2012年の初め以降、中国の銀行株を少なくとも140億ドル(約1兆7000億円)相当を売却したという。投資先としての中国の落日ぶりを象徴するのが、ブラジル、ロシア、インドを含む4カ国に投資する「BRICs(ブリックス)ファンド」をゴールドマンが閉鎖したことだ。ゴールドマンはBRICsの「名付け親」として新興国投資ブームを作ったが、中国が人民元を突如切り下げた時期にあたる8月12、13日の会合で閉鎖を決め、10月に別の新興国向けファンドと統合した。「予見できる将来に資産の急増が見込めない」と閉鎖理由を説明している。>(同上)「ゴールドマン」は、「儲かるから中国を助け」「儲からなくなったから中国を見捨てた」「国際金融資本」と中国の真実の関係も、同じでしょう。「国際金融資本」は、「儲かる」から中国を育て、「儲からなくなった」から中国を見捨てている。起こっている事実を完全に無視して、「国際金融資本と中国は『愛』で結ばれた『オシドリ夫婦の』ようだ」と信じつづけるのはやめましょう。最近、「日本の大手企業が続々と中国から逃げている」という話をしました。↓http://www.mag2.com/p/news/127959
日本の大企業だけではありません。欧米の大手金融機関も、続々と逃げ出している。中国はまさに、「沈みいくタイタニック号」といえるでしょう。皆さんも是非お気をつけください。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kanekashi.com/blog/2015/12/4624.html/trackback